
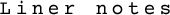
ビートルズがEMIスタジオで行った録音作業を、現存する音源で時系列に追う全スタジオ・セッション・シリーズ。現在までに以下の5作品がリリースされている。
『ワン・デイ・セッション(EGDR-0018)』
『フロム・ミー・トゥ・ユー・セッション(EGDR-0019)』
『EMIスタジオ・セッションズ 1964(EGDR-0021)』
『EMIスタジオ・セッションズ ’64-’65(EGDR-0022)』
『EMIスタジオ・セッションズ ’65-’66(EGDR-0023)』
本CDはその第6作目となる。革新的サウンドを聴かせた『リボルバー』を発表し、初の日本公演から、フィリピンでの大統領のレセプションを断わったことからの暴動騒ぎ。そしてジョンの「キリスト発言」による米国での炎上事件から、最後の全米ツアー。ひときわ激しかった1966年を走りぬけたビートルズ。
3ヶ月の休暇後の11月下旬から開始されたセッションは、ロック史上に燦然と輝くトータル・アルバム『サージェント・ペパーズ』となって結実するが、本CDは、そのアルバムに先駆けるシングル盤として「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー/ペニー・レイン」という、史上最強のカップリングが生まれるその過程を音で辿る内容となっている。
最後と決めて臨んだ全米ツアー。最終日である1966年8月29日、サンフランシスコのキャンドルスティック・パークでのコンサートを終えたビートルズは、映画撮影の仕事があるジョン以外は、3ヶ月の休暇を取る。ジョージはパティと連れ立ってインドへ向かい、1ヶ月近く滞在してラヴィ・シャンカールのもと、シタールの指導を受ける。
ジョンは9月5日に、リチャード・レスター監督による映画『ジョン・レノンの僕の戦争/原題 :How I Won The War』の撮影のため、ドイツへ飛ぶ。到着するなり、ジョンはまず髪を切り落とし眼鏡をかける。ライヴ活動の休止。喧騒から逃れ、そこに期するものもあったのだろう。もともと近視のジョン。公式の場ではサングラス以外は眼鏡をかけることは避けていたが、以降、眼鏡はジョンのスタイルになる。
休暇中であっても、リンゴは妻モーリーンと、ジョンが撮影で滞在するスペインへ激励を兼ね訪れたり、ポールはマネージャー、ブライアン・エプスタインと連れ立ってパリでジョンと落ち合ったりと、プライベートでも仲のよさがうかがえる。
ポールは映画『ふたりだけの窓/原題:Family Way』のサウンドトラックの準備をするかたわら、恋人ジェーン・アッシャーの導きもあり、ロンドンのギャラリーで行われるアート系のイベントにちょくちょく顔を出しては刺激を得ていた。当時のロンドンでは、アートや絵画、ビート文学やファッション、そしてポップミュージックが溢れ、多くのアーティストたちが、アンダーグラウンド・シーンで刺激しあいながら静かに浮上の時をうかがっていた。その流れの中、ジョンはロンドンのインディカ・ギャラリーでヨーコの展覧会に出向き、ふたりの運命的な出会いが生まれるのだ。
こうやって後から振り返ると、すべてが連鎖しているように思える。まさに創造のムーブメントだ。
久しぶりの休暇を思い思いに過ごし、ビートルズの4人はレコーディングの初日、11月24日にEMIスタジオに集結する。
レコーディング初日にジョンが用意した曲は、映画撮影期間中にスペインで思いついたという「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー」だ。年少期に遊んだ近所の施設、救世軍による孤児院「ストロベリー・フィールド」を題材にした曲だが、両親を早くに失ったジョンが、無意識下に感じていただろう孤独感など、自らの心象風景を抽象的に表わす言葉があふれていた。
♪ストロベリー・フィールズ・フォーエバー(概訳)
さぁ、ストロベリー・フィールズへ行ってみよう
現実なんてないのだから
心配はいらないさ
ストロベリー・フィールズは永遠
人生はたやすい 目を閉じてさえいればね
目にするものすべては誤解を生む
生きていくのは難しいだろうけど
僕にとってはどうでもいいことさ
どうやら僕の樹には誰もいないようだ
きっと高すぎるのか 低すぎるのか
つまり僕は誰にも理解されないってこと
でも大丈夫 それも悪くはないさ
スペインから戻ってから、この曲を仕上げたジョンは、3ヶ月ぶりにメンバーが揃ったEMIスタジオでギターを弾いてメンバーに聴かせた。ジョージ・マーティンは「すごく素朴で、文句なしに素晴らしかった」と記憶している。このCD1曲目、ジョンの弾語りで歌われる「take0」がそれに近いだろう。ジョンが、ムーディ・ブルースのマイク・ピンダーから入手したという、当時、開発されたばかりの楽器メロトロンを持ち込み、それをポールが弾いた。メロトロンは、フルートなど様々な楽器の音色がプリセットされたキーボードで、この曲のイントロで世界的に有名になる。
「take1」では、そのイントロはまだなく、ジョンの歌から始まるが、そこでメロトロンは伴奏に回っている。2番からジョンのギターが加わり、サビでジョージのスライドギターが出てくる。キーはBだ。
3曲目の「take1+dubs」は、「take1」にポールとジョージの鮮やかなコーラスがダビングされたバージョンだ。サビの♪Nothing to get hung aboutからジョンのボーカルがダブルトラックとなっていて、公式ボックスセット『サージェント・ペパーズ・50周年スーパー・デラックス・エディション』に収録されたバージョンとも微妙にミックス具合が違うものだ。
この日、4日ぶりのスタジオ入り。「take2」はキーがAへ1音下げられ、メロトロンによるイントロのあと、サビから始まるように構成が大幅に変更されている。「take4」では、気だるいジョンのボーカルがなんとも言えぬ雰囲気だ。メロトロンやドラムのフィルイン、ジョージによるスローテンポにしたロカビリー風のアルペジオのエレキギターのアレンジも固まってきたようだ。ポールも控えめにベースをダビングしている。
この日は再びベーシックトラック(伴奏)から録り直したようで、前回よりも少しだけテンポを速めた「take6」は、素晴らしいバージョンだ。そのあと「rehearsal」をはさんで、「take7」がOKテイクとなる。これが公式バージョンでも前半部分(1分経過部分まで)だけ採用される。その経緯は後述する。
ポールは12月1日、「グッド・ラヴィン」をヒットさせた米国グループ、ヤング・ラスカルズの来英コンサートに出かけ、2日はファンクラブ用レコードの録音。そして6日はキャバーン時代のレパートリーの「ホエン・アイム・シックスティー・フォー」の録音に取り掛かり、8日に再び「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー」をリメイクする。これはジョンの「別のアレンジでも試みたい」意向に沿ったものだ。ジョージ・マーティンは、トランペットとチェロのアレンジを用意し、演奏家たちを15日にスタジオに呼ぶ手配をした。
新しいアレンジへ向かうために、まずはリズム・セクションを見直すことからはじめる。ポールとジョージはティンパニーとボンゴ、マル・エヴァンス(ローディ)はタンバリン。ニール・アスピノール(結成当初からのスタッフで、アップルを40年間支えた)も参加してパーカッシヴなトラックを再構築している。この11曲目の様なサウンドだ。リンゴは逆回転ハイハットまで加えている。
トランペットとチェロが加わり、なんとも不思議なサウンドができ上がる。ジョージ・マーティンのクラシック調の管弦アレンジが、テンポアップされたダンサブルなビートと交じり合い、逆回転ハイハットがフリークアウト具合を演出する。サビの♪Strawberry Fields Foreverと歌った直後のブレイク部分にはジョージがソードマンデル(インドのキラキラした音色の弦楽器)のアルペジオを重ね、サイケデリックとスウィンギン・ロンドンの魔法の粉が振りかけられる。ちょっとダウナー系だが落ち着いたスローな「take7」とは対照的に、狂気じみた喧騒感漂うトリップソングだ。両者は似ても似つかない、全く違う曲と言える。
6日に録音した「ホエン・アイム・シックスティー・フォー」に、ジョンとジョージのコーラスなどをダビング。ここでのミックスでは、後半でジョージのエレキギターが大きく聴こえる。ボードヴィル調のポール作のこの曲、キャバーン時代にはおふざけで披露していたらしい。そのレパートリーが、なぜ復活したのか。一説にはポールの父ジェイムスが7月に64歳になったから、という話だ。
さて、2つのバージョンが作られた「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー」は、どうなったのか。両者を聴いたジョンは、G・マーティンに言う。「君ならできる。2つのバージョンを繋いでくれ」。それぞれキーもテンポも違う「take7」と「take26」をG・マーティンは見事に繋げて、それが今日聴ける公式バージョンとなる。
曲が始まってちょうど60秒のところ、歌詞で言うと以下の★のところで、take7からtake26へ切り替わる。
耳をそばだてて18曲目を聴いていただけたら、つなぎの部分で音質が変わるのが分かるだろう。ここに収録したバージョンはアナログシングル特有のミックスで、2度目のサビ後のブレイク部分のソードマンデルのアルペジオが9音のところ8音しか聴こえないレアミックスである。ジョンのボーカルのリバーブが少ないなど、ほかにも微細な差異がある。
「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー」と両A面シングルとして1967年2月に発売される「ペニー・レイン」が初めて取り上げられる。ポールはピアノのサウンドに凝っていたようで、ギター用のVOXアンプからリバーブをかけて鳴らし、ハーモニウムを重ねた。19曲目でその一端を聴くことができる。
ビートルズは年末の12月30日にもスタジオ入りし、「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー」と「ホエン・アイム・シックスティー・フォー」を仕上げたところで、既に午前3時に達していた。つまり大晦日の未明だ。そこで「ペニー・レイン」のダビング作業は翌年に再開することにして、新年を迎える。
新年は3日に、ジョージ・マーティンとエンジニアのジェフ・エメリックだけで、完成した2曲を米国へ送るためにマスターテープのコピー作業を行った。そして4日に全員がスタジオ入り。「ペニー・レイン」のダビングを再開する。
1月6日、この日はポールとジョージが「ペニー・レイン」にハンドクラップとスキャット・コーラスを重ねた。20曲目で、そのリハーサルの様子が聴ける。ここで2人が口ずさむフレーズが、後日ブラス・セクションでたどるメロディの元になる。
「ペニー・レイン」に、9日と12日にわたって、フルート4本、トランペット2本、フリューゲンホーン1台、オーボエ、イングリッシュ・ホルン、ダブルベースなどのダビングを試みる。21曲目で、そのセッションの様子が聴ける。ここまでが「take9」だ。
さらにポールは1月11日に、BBCテレビでバッハの「ブランデンブルグ協奏曲第二番ヘ長調」を演奏するディヴィッド・メイスンに目を留める。早速、彼を17日にスタジオへ招き、ピッコロ・トランペットを吹き込んでもらう。それが「ペニー・レイン」を印象付ける、あの高音のピッコロ・トランペットになるのだ。特に最終ヴァースでは大きくフィーチャーされ、米国プロモ・ミックスでは曲の演奏が終わった後も鳴り響く。
アルバム『サージェント・ペパーズ』では仮想ライヴショーのアンコールの位置に収録され、コンセプト・アルバムの最重要曲となる「ア・デイ・イン・ザ・ライフ」も、最初は「take1」のように素朴な曲だった。しかしこの曲も「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー」と同じ運命を辿り、ポールが書いて後日追加されるミドルパートや、オーケストラの重層なサウンドもダビングされ、1967年という時代の空気を包み込んだ壮大な曲へと生まれ変わる。
ここではまだポールのミドルパートは加えられていない。
11月24日から1月19日まで、約2ヶ月に及ぶレコーディング期間でこのCD1枚に4曲のみの収録ということは、ビートルズのレコーディング手法が劇的に変わったことを意味する。前作までなら、アルバム13曲すべてが完成する期間を費やしたのだ。時間にとらわれずスタジオ作業に没頭できる環境が、ビートルズの音楽的進化を加速させた。その勢いのままレコーディングは続けられ、4月21日にアルバム『サージェント・ペパーズ』は完成する。
録音テクノロジーの進化。コンセプト・アルバム。これまでのポップミュージックの概念をくつがえすアート性。数ヶ月前のロックンロール・バンドには、およそ想像もつかない発展を遂げたビートルズだったが、反面、全員揃わなくともレコーディング作業が進められることも増えた。それはグループという観点からは利点ばかりではなかったかもしれない。実際、ドラムを録り終えたリンゴはヒマを持て余し、「おかげでチェス上手になったよ」と振り返り、ジョージは「あの頃、僕の心はインドにあった」と回想している。それがやがて訪れる「グループとしての不協和音」の兆しとなっていく。枠をぶち破っていく創造性、一丸となって取り組むグループ作業から、作品完成を主眼とする個性の発露。
そうやってビートルズは、これまでどのロックバンドも経験したことのない領域へと入っていくのである。
CROSS(the LEATHERS/島キクジロウ&NO NUKES RIGHTS)