
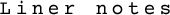
ジェームズ・ポール・マッカートニー
(Sir James Paul McCartney MBE/1942年6月18日生まれ )
Eternal Groovesからの本作は、非常に興味深い「ポールのベースプレイがはっきり聴けるミックス集」ということで、ポール・マッカートニーという稀代の天才コンポーザーのベース名演を堪能できる内容となっている。
ザ・ビートルズがデビューした1962年から60年、2022年の現在においても活動を続けているポール。その中でも、ジョン、ジョージ、リンゴとともに音楽制作をした60年代は、ロック・ミュージックの変革期であり、ビートルズはその先頭を走りつづけた。録音技術の革新もあり、アートやカルチャーも混ざり合うスリリングな時代。ポールのベースプレイも、わずか5年ほどの間に、目覚ましい進化を遂げていく。
そんな様子を音で辿るべく、ここにはほぼ年代順で収録されている。
ビートルズの黎明期はギターを担当したポールも、スチュワート・サトクリフの脱退を受け、ベースを担当することになる。コスト的にもヴァイオリン・ベースと呼ばれるセミアコ・ベース(ボディ内部が空洞)のヘフナー500/1を手に取り、それはやがてポールの代名詞ともなる。音質的にはサスティーンの少ないウォーミーな音を響かせるベースだ。「オール・マイ・ラビング」のベースの音といえば伝わるだろうか。
やがてエレキギターも進化し音圧が上がる時代になると、ソリッドボディのリッケンバッカー4001を弾くようになっていく。こちらは「ペーパーバック・ライター」で輪郭のはっきりした、その音質が分かるだろう。
演奏面に関しては、ビートルズ随一のテクニシャンでもあるポールだ。リズムの正確さや、ノリの良さは、それぞれの楽曲に刻まれている。
なお、本作はマルチトラックからベースを大きくミックスされた音源を集約したとのことで、ただイコライザーで低音域を上げただけではないことが一聴して分かると思う。曲によっては、フェイドアウト後もベースが聴こえるテイクもある。
早速、聴いていこう。
本国では1963年11月22日発売のセカンドアルバムで発表された。わずか5ヵ月前のファーストアルバムの録音時には、オリジナル曲が足りずカバー曲で補填していた彼らだったが、「プリーズ・プリーズ・ミー」、「シー・ラブズ・ユー」とヒット曲の書き方をジョンとポールがつかみかけていた時期。ロイ・オービソンとのツアーの合間に、ポールがひらめいてバスの中で書いたといわれる。
ポールが弾く4ビートのベースラインに、ジョンの6連のサイドギターが心地よい。ギターソロの後の3番の歌が始まって4小節目のベースが一音コードミスをしている。これは、ポールが歌とベースを同時に録音しているからだろう。
いわゆる「ウォーキング・ベース奏法」は、1小節の音数こそ少ないものの、ノリの出し方が難しいし、ましてや歌いながらの演奏なのだ。まるで熟練のベーシストのようなプレイ。この時、ポールは21歳である。
「オール・マイ・ラビング」と同じ1963年7月30日の録音。いきなりジョンの声で始まり、ポールとジョージのコーラスが追いかける。ビートルズらしいコーラスワークの魅力にあふれる。ジョンが「シングルにするつもりで書いたけれど、アルバムにまわした」というとおり、確かにヒット曲としては弱いかもしれないが、インパクトは強烈。ファンにも人気が高い。
展開部では、のちの「ヘルプ!」のような、コーラスが別の歌詞で追いかける手法が聴ける。エンディング直前のポールの「イェー」の連呼が、もはややけくそ気味で面白い。そしてビートルズの特徴でもあるが、曲の終わらせ方にも手抜きは無し。エンディングだけのための見事なコードワークで曲を締めくくっている。
この時点での自分たちのすべてを注ぎ込んだ。いや、注ぎ込みすぎて再現不能となったのか、ライヴ演奏は一度もなされなかった。そんな話題盛りだくさんの、愛おしい曲だ。
1964年になり、初の主演映画とアルバム『ア・ハード・デイズ・ナイト』のセッションが行われる。ジョージはリッケンバッカー社の12弦エレクトリックギターを手に入れ、さっそくこの曲に活用する。英国ではシングル「キャント・バイ・ミー・ラブ」のB面として1964年3月20日に発売。
ジョンは「ウィルソン・ピケットを狙った」と発言し、R&Bへの憧憬を感じさせる。ジョージの12弦ギターの響き、珍しいジョンのギターソロと、興味がつきないが、実はポイントはベース・プレイにある。
1番の歌のバックで、1拍、2拍、3拍と拍子の頭だけを弾く、R&Bフィーリングのベースプレイなのだが、4拍目に強烈な4連符の速いパッセージを差しこんでいる。このベースプレイが効いているからだろう。ロックンロールに黒っぽさが加わり、なんとも言えない魅力がある。
この演奏は、ポールが敬愛する黒人ベーシスト、ジェームス・ジェマーソンを意識してのことだ。J・ジェマーソン(1936年1月29日 – 1983年8月2日)はモータウン・レコードの幾多のヒット曲を支えたベーシストとして知られる。テンプテーションズの「マイ・ガール」、マーサ&ザ・ヴァンデラスの「ダンシング・イン・ザ・ストリート」、スモーキー・ロビンソン&ミラクルズの「ゴーイング・トゥ・ア・ゴーゴー」でのプレイは燦然と輝き続けている。
この曲でビートルズは、初めて明確に演奏面でR&Bへのアプローチを始めたのだ。
1964年2月27日の『ア・ハード・デイズ・ナイト』のセッションで録音された。
モノ、ステレオ、映画でそれぞれミックスが違う。3人のコーラスワークがダブルトラックで録られていて、「黒人女性コーラス・グループの感じを狙った」とジョンが語ってるとおり、歌声がキラキラしている。
ポールは「オール・マイ・ラビング」同様に、見事なウォーキング・ベースで演奏をひき締めている。
1965年の映画&アルバム『ヘルプ!』のセッションから、1965年2月18日に録音。このアルバムの録音では、キーボード演奏に目覚めたメンバー自身によるオルガンやエレピのサウンドが特徴的で、この曲もまさにそうだ。
ギターはジョージの1本だけで、ジョンはギロを鳴らす。シンプルな編成だけに、ポールの安定したベースが曲を支えている。
クリスマス・シーズン向けに英国での11枚目のシングルとして、1965年10月16日に録音され、「恋を抱きしめよう」と初の両A面として発表。アルバム『ラバーソウル』の録音と同時進行で制作された。
印象的なギターリフに始まり、ベースも重なっていく構造は、ロック・バンドのアレンジの原点だろう。
アルバム『ラバーソウル』のセッションで1965年11月3日の丸一日をこの曲のみに充てて制作された。録音は深夜までおよび、やがてそれは慣例となる。
ビーチ・ボーイズのブライアン・ウィルソンのルート音(その小節のコードの音)とは違う音をわざと使うベース奏法を参考にしたようだ。イントロのギターはFmで始まるがベースはC音で始まり、まるで裏メロのように音符を配していく。
「この曲でベースの楽しさに開眼した」とはポールの弁。
アルバム『ラバーソウル』セッションの最終日、1965年11月11日にかけこみで録音され完成した。ここでもポールは、J・ジェマーソン風の演奏で、手数の多いベースラインを聴くことができる。ピアノもポールが弾いており、有機的にからまる様は天才ポールの独壇場だ。
サウンド面でも変化があり、この『ラバーソウル』セッションから、ヘフナーに代わりリッケンバッカー・ベースを使用している。より鮮やかなベース・サウンドを求めての選択だった。
オーティス・レディングの「リスペクト」でのドナルド・ダック・ダンのベースプレイにヒントを得たという、黒っぽいロックンロールだ。アルバム『ラバーソウル』のセッションでも初期の1965年10月13日録音だ。
諸説あるギターソロは、ポールがオープンチューニングで弾いたスライドギターだ。フレーズ的にはわざわざスライドで弾くフレーズでもないし、スライドで弾くならもっと風味を効かせた方がポイントは高くなるはずだが、この時はとにかく「スライドギター」をやってみたかったのだろう。
モータウンのR&B流儀に、ブルースのスライドギターを落とし込む。「こんなのまだ誰もチャレンジしてないゼ!」とワクワクしながら録音してるポールたちが目に浮かぶ。
1965年11月10日に録音された、邦題「愛のことば」。これもまたブラック・ミュージックへのリスペクトが詰まった曲とアレンジだ。ポールのベースは実にブラック・フィーリングにあふれている。サム&デイブの「ホールド・オン・アイム・カミング」と同じコード展開なのも微笑ましいが、ジョンとポールの歌いっぷりは見事だ。
終盤に出てくるオルガン(ハーモニウム)はジョージ・マーティンが弾いているが、この弾き方は紛れもない「ブラックを吸収したロック」だ。クラシック畑のプロデューサーも、ビートルズのロックに感化されたかのようだ。
最初期のメッセージ・ソングのひとつで、ジョンとポールはマリファナをやりながら、明確な意図をもって「ラブ&ピース」を歌に託した。
7枚目のアルバム『リボルバー』のセッションで1966年4月13、14日に録音され、12枚目のシングル盤として6月10日に発売された。ここで録音方式に新たなアイデアが取り入れられる。ベース録音に関して、ラウドスピーカーをマイクとして録音すると、音がより明確になることを発見したのだ。アメリカのウィルソン・ピケットのレコードのベースが、ビートルズの作品よりもラウドに聴こえる理由を探求し続けたビートルズとエンジアたちの成果だった。
単調になりがちなロックンロールに、横ノリのグルーヴを生み出すこのベースプレイを感じて欲しい。
1966年4月14日に録音され、シングル「ペイパーバック・ライター」のB面として発表された。テープスピードを落として録音し、逆回転なども加えて、サイケデリック元年にふさわしいサウンドを作り上げたのだ。
ポールのベース・プレイも自由自在に駆けめぐる名演だろう。
特に♪レーイインとうたわれるサビ部分のベースプレイは冴えわたり、1’36″あたりでは必殺の2拍3連フレーズが出現。この曲の魅力を決定づけるグランドスラム級の活躍だ。
1966年4月20日に『リボルバー』セッションで録音され、アルバムの1曲目をジョージの曲として初めて飾った。ファンキーなポールのベースプレイが遺憾なく発揮された、この曲。0’53″あたりからの、スタッカートした16分音符の速いフレージングは必聴ものだ。
いまや定説となった「ジョージの曲になると、ポールのベースプレイがすごい」の好事例だろう。ノリに乗ったポールはギターソロまで弾いてしまうが、それだけではなく、ソロ後の1’32″あたりからは、ギターリフまでダビングしているようだ
英国での14枚目のシングルは「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー」と両A面扱いでリリースされたが、英国チャートではトップを取れず。しかし、今では史上最高のシングルの1枚であることに異論はないだろう。
1966年12月29日から翌年1月25日までかけて録音。これだけの時間が費やされるのも、慣例破りであった。フルート、トランペット、オーボエ、コントラバスにピッコロ・トランペットと管楽器がフル動員され、個性的なコード進行とサビでの転調。ロックの枠を軽々と超越した展開、構成にため息が出る。
イントロ無しで、いきなりベースの高音フレーズでのオープニング。ポールのベースの音符の微妙な長短、配し方に注目して欲しい。
1967年3月29、30日に録音され、アルバム『サージェント・ペパーズ』に収録された。シンプルなバンド演奏に、ポールの歌うようなベースが、リズムと流れを生み出している。ポールのベース演奏史上でも名演のひとつに数えられるものだ。
このころから、ベースをミキサー卓へダイレクトにつないで録音する「DIボックス」を活用するようになっていた。これにより、ベースを後からダビングする作業が可能になったことが大きい。ポールは語る「後からベースを録音するのが好きなんだ。自由にやれるからね」。
この録音手法はビートルズに多くの音楽的成果をもたらした。一方で、ひとつの曲をメンバー全員が揃って録音する機会は減っていった。ジョージは述懐する。「僕はビートルズの一員でいることに、興味を失っていった」
1967年3月9日から23日までかけて録音し、アルバム『サージェント・ペパーズ』に収録された。
ポール「だんだん良くなるぞ!」
ジョン「これ以上悪くならないサ」
2人の個性が反映された歌世界。ポール主導で書かれ、ジョンがとても重要なDV告白の部分を書いた。この曲もベースは後からダビングされ、ポールが縦横無尽にベースを操る。1番サビ(0’25″〜)と2番サビ(1’01″〜)では、まったく違うベースのフレーズを聴くことができるだろう。こんなアプローチってポップ・ミュージックではまずあり得ない。曲全体を俯瞰し、ひとつの作品としてコントロールしている、至高のベース・アレンジだ。
1967年1月19日〜2月22日にわたり録音されたアルバム『サージェント・ペパーズ』を象徴する壮大なナンバー。
ジョンの曲とポールの曲を合体し、やはりポールがベースをあとからダビングした。つぎはぎの曲が不自然に聴こえないのは、ポールのベースによるところが大きい。
1963年10月17日、ビートルズにとって初めて4トラック・レコーディングされた曲で、ここではボーカル、ベース、ドラムのみのミックスで聴ける。2番のド頭のコード音をポールが間違えているのも、はっきり聴こえる。
と、ポールが言ったかは不明だが、ポールはベーシストとしてもコンポーザーとしても、ブライアン・ウィルソンを意識していた。
天才は天才を知る。2人に共通するのは、プロデューサー的な見地から俯瞰して楽曲をとらえてアレンジする能力を、作曲能力とともに有していたことだろう。2人の大西洋を越えた交流は、ロック界にも多くの名曲を生んだ。
ポールが、どのように考え、そのフレーズを選択したのか。そんなことに思いを巡らしながら聴くことのできる作品集だ。
CROSS(the LEATHERS/島キクジロウ&NO NUKES RIGHTS)