
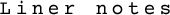
「世界ジャズ・フェスティヴァル、7月中旬、日本で3部にわけて」と報じたのは、1964年2月7日の毎日新聞(夕刊)である。
「ニューポート、モンタレーなど、アメリカの大ジャズ・フェスティヴァルと同じスケールのジャズの祭典が、7月中旬、日本でも行なわれることになった。JBC(ジャパン・ブッキング・コーポレーション)の主催する世界ジャズ・フェスティヴァル。20組近い有名楽団、プレイヤー、歌手が来日し、これに参加する。計画は本決まりになっている。日本のジャズ、ポピュラー界初の大行事になることは間違いない。
今回のジャズ・フェスティヴァルは、〈モダン・ジャズ〉〈スウィング&ディキシーランド・ジャズ〉〈ポピュラー〉の3部門に大別され、東京、大阪、名古屋で同時開催される。つまり、東京でモダン・ジャズをやっている日は、大阪でスウィング&ディキシー・グループというふうに。そのほか、京都、札幌でも開催される。開催期間は7月10日から16日までで、東京は6日間、その他の地域は2日間開かれる」(毎日新聞)
このフェスティヴァルに参加したのがマイルス・デイヴィスだ。これ以前にも来日の噂はあったが、ここに初めての来日公演が実現することになった。「ジャズ界の帝王」と呼ばれるマイルスが、新加入したサム・リヴァースと、集められて1年以上がすぎた、ハービー・ハンコック、ロン・カーター、トニー・ウィリアムスのリズム・セクションを伴い、日本で行なわれた初の国際的なジャズ・フェスティヴァル「第1回世界ジャズ・フェスティヴァル」(1回だけで終わってしまったが)に参加したのである。
マイルスは38歳の誕生日を迎えたばかりで、名実共にジャズ界における第一人者の地位を確立していた。まさに「待望の」という言葉がピッタリの初来日だった。メンバーはほとんどが無名である。それでも、ハービーやカーターは、「すごい新人」との噂が広がっていた。来日2週間前に加入したリヴァースについては、フリー・ジャズ系のミュージシャンであることしか情報はなく、わずか18歳のトニーは「天才少年」との呼び声が高かった。
1926年にイリノイ州アルトンで生まれたマイルスは、45年にモダン・ジャズがひとつのピークをきわめていたニューヨークのジャズ・シーンでデビューを飾る。チャーリー・パーカー、ディジー・ガレスピー、セロニアス・モンクといった、若く創造的なミュージシャンがニューヨークではすでにビバップを演奏し、しのぎを削っていた。マイルスは、そのパーカーやガレスピーを師と仰ぎ、研鑽を重ねていく。
40年代中盤からの数年間がマイルスにとっては下積みの時期だ。最初に大きな注目を浴びたのは、48年秋に自身の9重奏団でニューヨークのジャズ・クラブに出演したときのこと。ここには、のちにいくつもの重要な仕事を一緒にするアレンジャーのギル・エヴァンスが参加していた。
ビバップはアドリブを重視した熱狂的な演奏が売り物だった。しかしこの9重奏団は、マイルスの意図の下、アレンジ主体の抑制されたサウンドでビバップとは対極に位置する演奏を行なっている。この新人時代から、彼はシーンに一石を投じる独創的なスタイルの持ち主だった。
マイルスのキャリアを大きくわけるなら、60年代末までのアコースティック時代と、それ以降のエレクトリック時代になる。アコースティック時代の彼は常にモダン・ジャズの世界で最先端にある演奏を行ない、シーンをリードしていた。
エレクトリック時代に入ってからは広くポピュラー音楽全般に影響をおよぼしていくが、それ以前の40年代末から60年代末までの約20年間はジャズ界における最高のイノヴェーターとして君臨したのだった。
この時代、マイルスはスタンダード曲に独特の表現を加えて独自のスタイルを生み出し、一方でモード・イディオムを導入し演奏の可能性を大きく拡大している。さらには、ジャズ史上最高のコンボと呼ばれるクインテットを2度にわたって結成したり、ギル・エヴァンスと組んだオーケストラ・ワークではそれまでのジャズにない斬新なサウンドも創造したのだった。その彼がついに日本のファンの前に姿を現したのだ。
フェスティヴァルは、3つのグループにわかれ、東京、大阪、京都、名古屋、札幌の各会場で7月10日から16日まで連日開催された(各グループには1日のオフがある)。
Aグループ(モダン・ジャズ) マイルス・デイヴィス・クインテット、J.J. ジョンソン・オールスターズ、カーメン・マクレエ、ウィントン・ケリー・トリオ、松本英彦カルテット
Bグループ(スウィング&ディキシーランド・ジャズ) ジーン・クルーパ・オールスターズ、レッド・ニコルス&ヒズ・レッド・ペニーズ、デュークス・オブ・ディキシーランド、エドモンド・ホール、ダコタ・ステイトン
Cグループ(ポピュラー) トミー・ドーシー・オーケストラ、フランク・シナトラ・ジュニア、パイド・パイパーズ、ジェニー・トーマス、ルイ・ベルソン
マイルス・クインテットが参加したAグループのスケジュールを纏めておこう。
7月 10日 「名古屋市公会堂」
11日 「大阪フェスティバルホール」
12日 「日比谷野外音楽堂」
13日 「大阪フェスティバルホール」
14日 「東京厚生年金会館大ホール」
15日 「京都市円山公園音楽堂」
フェスティヴァル出演の一行は、7月9日の4時と8時の飛行機に分乗し羽田空港に到着した。マイルスと夫人のフランシスはCグループと一緒に4時の日航便で日本の土を踏む。当時の羽田にはゲイトの設備がなく、小雨の中、傘をさしたふたりがタラップから降りてくる写真を『スイングジャーナル』誌の9月号が掲載している。
マイルスはフランシスをサポートし、出迎えた関係者やファンに手を振り、終始笑顔を向けるなど、伝えられる傲慢な素振りは微塵も見せなかった。しかしロビーから空港内のバーに直行し、用意された記者会見をすっぽかしたところは、いかにも彼らしい。
8時の飛行機で到着したAグループとBグループを待って、空港で10時から簡単な記者会見が開かれたが、そこにマイルスの姿はなかった。
3つのグループではAグループに人気が集中。東京ではAグループが日比谷の「野外音楽堂」と新宿の「厚生年金会館大ホール」に登場し、後者では当日に1000円の立ち見券が売り出され、これにファンが殺到。会場は立錐の余地がないほどの満員だった。
プログラムは、マイルス・クインテット、ウィントン・ケリー・トリオ、松本英彦カルテット、カーメン・マクレエとノーマン・シモンズ・トリオ、最後がJ.J. ジョンソン・オールスターズで、3時間半にわたって熱演が繰り広げられた
Aグループのコンサートでは、マイルスのクインテットがトリを飾ることになっていた。これが、初日の朝にトップ・バッターとして登場することに変更される。サウンド・チェックが終わってから出番までの時間が長く、楽屋で待機するのを嫌ったためだ。
来日2週間前にテナー・サックス奏者がジョージ・コールマンからサム・リヴァースに交代したことは事前に告知されていなかった(パンフレットにはコールマンの名前が掲載されている)。そのため、ステージが終わってもコールマンだと思っていたひとが多かった。
いくつかのゴタゴタはあったものの、コンサートの幕が切って落とされるや、この時点での最新作『セヴン・ステップス・トゥ・ヘヴン』(コロムビア)を録音した1年数か月前の演奏と比べ、マイルスおよびクインテットがいかに前進していたか、そして変貌していたかを、ファンは思い知らされることになった。
最大の要因はリヴァースの加入である。マイルスにとっても、彼の参加はプレイに大きな変化を呼び起こすものとなった。ただし、リヴァースの存在はある意味で両刃の剣だ。彼がグループを刺激したことは間違いない。ところが、他の4人と明らかにコンセプトの違うリヴァースの参加が、それまで築いてきたグループのサウンドをいい意味で崩壊させてしまった。
日本公演では、14日に行なわれたコンサートが『マイルス・イン・トーキョー』(CBS・ソニー)として発表されている。しかし、「日比谷野外音楽堂」(本作)と「京都円山公園音楽堂」のライヴも関係者が記録用に録音していた。それらもすでに海賊盤で紹介されていたが、ここに正規盤として発売されることになった。
これらの公演の素晴らしさは『マイルス・イン・トーキョー』で証明済だ。本作に収録されたのはそれより2日前に残されたものである。そして、こちらもそれに勝るとも劣らない素晴らしい演奏で聴き手に迫ってくる。
日本公演ではグループに溶け込めないリヴァースのもがきが露呈していた。しかし、それすらポジティヴな要素にしてしまうのがこのときのマイルスだった。居直りともとれるリヴァースの個性的なプレイを受け、マイルスもグループのサウンドより個人のプレイに徹してみせる。彼の加入は、マイルスのグループにさまざまな形でそれまでとは違う個性と演奏のあり方を獲得させたのだった。
「日本では毎晩すごい演奏ができた。サムが張り切ったプレイをしていた。マイルスも触発されたし、わたしたちリズム・セクションも煽られっぱなしだった」(ハービー)
リヴァースを推薦したトニーは、どう感じていたのだろう?
「初めて日本に行って、まずびっくりしたのは日本のファンがジャズをとてもよく理解していたことだ。正直なところ、不安だった。どれだけ受け入れられるかわからなかったからね。でも、毎回、大きな拍手で迎えられた。マイルスも珍しく興奮していたみたいだ。それで、演奏がどんどんハードになっていった。たった1週間で、クインテットの演奏は大きく変わった。それが、次にウェインが入って実を結ぶ。きっかけはサムだ。彼がクインテットのサウンドを変えたのさ」
しかし、リヴァースの参加はわずかな期間だけだった。日本公演とその後にアメリカで行なわれた数回のギグにつき合っただけで終わってしまう。前任者のジョージ・コールマンと後任のウェイン・ショーターのつなぎだったのだ。
これまで、リヴァースが加わったマイルス・クインテットの作品は、公式には『マイルス・イン・トーキョー』以外に残されていなかった。ところが今回、このときの京都と日比谷野の演奏がそれに加わったことは史的にも大きな意味がある。
コンサートの内容とはまったく関係ないが、新宿でジャズ喫茶の「DUG」を経営し、60年からジャズ・フォトグラファーとしても活躍している中平穂積の話を最後に紹介しよう。
「厚生年金会館大ホールでは撮れなかったんです。呼び屋さんは、ぼくが写真を撮るのを知ってたから、日比谷の野音でも、最初から『撮影禁止』といわれていました。それで、どうせなにかいわれるだろうと思ったから、わざとカメラをぶら下げて行ったら、『中平さん、今日は禁止だから、カメラ預かるね』。
ぼくは友だちにもカメラを持たせて(笑)、それで撮ってたんです。そうしたら、また見つかって。その場でカメラのふたを開けさせられて、フィルムをビリッですよ。それでも写真が残っているのは、もう1台用意してあったから(笑)。だけど、ほんの2、3枚しか撮ってないです。あのころは、呼び屋さんに怖いひとがいて、今度見つかったらそれこそ殴られると思って(笑)」
このジャケットに使われたのが、そのときの貴重なライヴ写真だ。
[(c)WINGS 21083045:小川隆夫/TAKAO OGAWA]