
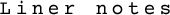
マイルスの初来日時に残された京都のライヴ盤である、来日の経緯は同時に発売された「日比谷野外音楽堂」ライヴのライナーノーツに書いておいた。
識者の間で、このときのコンサートはどう評価されたのだろう? 『スイングジャーナル』誌の9月号には、「モダン・ジャズ・グループを聴いて」と題した座談会で、評論家の久保田二郎とピアニストの八木正生が次のように話している。最初が久保田で、次が八木の意見だ。
「レコーディングと生のステージではかなり内容が違うといわれていたけど、これはたしかですね。マイルスというひとは、スタジオ録音のときには別の演奏をしている。彼のレコードからは独特のムードが伝わってくるが、生を聴いたときに感ずる、あの緊迫感はないからね。恐ろしいくらいの緊迫感と、それを通じて生まれる清楚美ね。そういった点で、マイルスの生を高く買うな」
「前衛ジャズには、『いろいろと実験しています』『これが実験なんだ』といった実験臭があるものだけど、マイルス・ジャズからは、そのような試みがあっても、実験臭を感じることがないですね。むしろ、マイルスを聴いていると、この次に来るジャズがどんなものかがいちばんよくわかる気がする」
アメリカから同行した評論家のレナード・フェザーは次のように報告している。
「小柄なイタリアン・スーツを着た端整なアメリカ人が、シャンソンの〈枯葉〉が持つ翳りある最初のテーマ・メロディを吹き出すやいなや、嵐のような拍手が沸き起こった。あの興奮は、フェスティヴァル全体を通して、他に比較できるものがなかった。マイルスのコンサートは5000席(実際は約3000席)ある日比谷野外音楽堂を満員にし、次いで厚生年金会館大ホールでも行なわれた。
しかし、ツアーの中でもっとも印象的だったコンサートは京都の円山公園音楽堂でのものだ。マイルスのセットの間に小雨が降り始めた。雨は次第に強くなっていったが、80人程度の若いファンがステージ脇の屋根がある場所に移った以外、数千人の聴衆は雨に打たれるまま席を立とうとしなかった。傘を持っていたのは数百人くらいのものである。
マイルスのセットが終わり、彼が花束を受け取ったのち、カーメン・マクレエがステージに登場し〈ヒアズ・ザット・レイニー・デイ〉を歌い始めた。そのとたん、雨はピタリとやんだのだ!」
このフェザーを中心に、ディスク・ジョッキーのジミー・ライオン、「モンタレイ・ジャズ・フェスティヴァル」の主宰者アイゼン・バーガー、日本側からは、油井正一、久保田二郎、中村とうよう、榛名静男(『ダンスと音楽』誌編集長)、白木秀雄、八木正生などが参加し、7月10日と11日に「世界ジャズ・フェスティヴァル・パネル・ディスカッション」が、新宿「厚生年金会館6階会議室」で開かれている。テーマは、初日が「ジャズ・フェスティヴァルのあり方」で、2日目が「ジャズの人種問題」という興味深いもの。
ところで、14日の「厚生年金会館大ホール」コンサートには、中学2年生だったぼくも、偶然のことだが行っている。ひょんなことからチケットを手に入れたのだが、そのころはジャズをほとんど知らなかった。家には『サンジェルマンのジャズ・メッセンジャーズ』(RCA)などのレコードはあったものの、マイルス・デイヴィスがどんな演奏をするひとなのかは知らなかった。
チケットは最後部の座席だった。印象に残っているのは、立ち見が出るほど混んでいたことと、タキシードに蝶ネクタイで出てきたミュージシャンの姿に、「ジャズってやけに気取ってるな」ということだった。1曲の演奏が長いことも印象に残った。それまでに観た外国人のコンサートといえば、同じ「厚生年金会館大ホール」で行なわれたトリオ・ロス・パンチョスぐらいのものだ。
マイルスの演奏はといえば、残念ながらほとんど記憶にない。のちに、『マイルス・イン・トーキョー』(CBS・ソニー)を耳にして、そういえば〈マイ・ファニー・ヴァレンタイン〉もやっていたっけ、と思い出す程度だ。
そんなおぼろげな記憶の中で、鮮明に覚えていたことがある。マイルスの音が非常にクリアなサウンドだったことと、耳をつんざくような鋭さでいちばんうしろの席にまで届いたことだ。これには度胆を抜かれた。「厚生年金会館大ホール」の2階席は、最後列に近づくほど急勾配になっている。その最後部にまで、彼のトランペット・サウンドは楽々と届いていた。
日本で残したマイルス・クインテットによる演奏が重要性なのは、なんといってもサム・リヴァースが参加していることだ。64年は、マイルスのグループが一度もスタジオに入っていない。ほかには、『マイ・ファニー・ヴァレンタイン』と『フォア・アンド・モア』(どちらもコロムビア)が、ニューヨークの「フィルハーモニック・ホール」で2月に実況録音され、帰国後の9月に、リヴァースからウェイン・ショーターに交代したクインテットで『マイルス・イン・ベルリン』(同)が録音されている。
スタジオで録音をしなかった事実は、その時点で「自分の音楽にもっともフィットするテナー・サックス奏者が見つからなかったから」といわれている。スタジオでは納得できる音楽を録音する——これがマイルスの流儀だった。
前任者のジョージ・コールマンはテナー・サックス奏者としてソツがなかったものの、マイルスが追求していた新主流派的な演奏からすれば、スタイルがやや古い。彼に比べると、リヴァースはマイルスより先を行くほどの音楽性を持ち合わせていた。マイルスの口ぐせのひとつに、「聴き手の1歩か2歩先を行く音楽を演奏するのがいい」というのがある。ただし、リヴァースのプレイはそれよりさらに先を行っていた。
この条件を満たすテナー・サックス奏者がウェイン・ショーターである。しかし、彼にはジャズ・メッセンジャーズでの仕事が残っており、コールマンが退団したときは、マイルス・クインテットへの参加が不可能だった。
リヴァースの言葉だ。
「最初から1か月ほどの参加が条件だった。わたしはボストンが本拠地だし、そのあとは自分のバンドで演奏する仕事が決まっていた。だから、マイルスのグループにとどまることはできない。彼も、わたしのことは一時的な参加と決めていた。数回演奏しただけだが、マイルスから得たものは大きかった。自分のエモーションにしたがって演奏すること──それがいかに大切かを学んだ」
リヴァースは、帰国後にブルーノートで吹き込んだリーダー作を契機に、フリー・ジャズの指導的ミュージシャンのひとりになっていく。
もう少しリヴァースがクインテットに在籍していれば面白いことになったかもしれない。しかし、マイルスはショーターを選んだのだ。その結果、60年代を代表するグループとして、マイルスのクインテットはジャズの先進的な部分を、これまで以上の勢いで発展させていく。
日本でのライヴは、60年代後半にマイルス・クインテットが到達した先鋭的で触発的なパフォーマンスを強く予感させる。その点でも、『マイルス・イン・トーキョー』と、今回、新たに登場した日比谷と京都のライヴ・アルバムは高く評価できる。
ところで、手元にこのときマイルスが出演した「第1回世界ジャズ・フェスティヴァル」のパンフレットがある。LPジャケットほどのほぼ正方形で、94頁、厚さ9ミリの豪華なものだ。当時の駐日米国大使エドウィン・O・ライシャワーの挨拶文が冒頭を飾り、ジャズを含むポピュラー音楽系の評論家を総動員した執筆陣が豪華だ。
中でも、安部寧の序文に感ずるものがある。
「正直に告白すると、わたしは、これだけ大規模なジャズ・フェスティヴァルが開かれること自体に、早くもある感動を覚えている。こんなにスケールの大きなフェスティヴァルが開かれるほど、ジャズ人口の底辺が広がったのかと、今昔の感に堪えないからだ。
敗戦後間もなく、10代のわたしたちが素朴に魅せられたジャズは、いまやもっと広い市民層の支持を獲得しているということなのである。
モンタレーやニューポート以上のジャズ・フェスティヴァルが日本で開かれることについて、貿易自由化、経済の高度成長とそれに伴う安定ムードなど、社会的背景を押し立てることはたやすい。だが、〈疎開児童上がり〉のわたしは、この催しを、なにより戦後19年という年月の重みで受け止めたい」
この文章を読んで、「戦後は遠くになりにけり」という言葉を思い出した。戦争を知らないぼくだが、それでも、東京オリンピック開催が現実のものとなり、日本の復興にはすさまじい勢いがあると、子供ながらに実感していた。そんなふうに思うのは、東京に住んでいたからかもしれないが、あれよあれよという間に、住んでいた渋谷の街が変貌を遂げていったことは、はっきりと覚えている。
ほとんど広告が載っていないこのパンフレットだが、中ほどに1頁を使った「品川ボーリングセンター」の宣伝がある。「世界最大120レーン」——こういうことにも、戦後の復興と、豊かさを思わずにいられない。しかも、風営法(風俗営業等取締法)の規制がなかったのか、夜は12時までだが、休前日は午前3時までの営業で、おまけに毎夜6時から11時まで「一流バンドの演奏あり」となっている。どんなバンドが出ていたのだろう?
話を戻すなら、本作は初来日公演における最終日のステージを収録したものである。個人的な好みだが、「厚生年金会館大ホール」と「日比谷野外音楽堂」以上にこの「京都円山公園音楽堂」でのパフォーマンスは優れている。6日間、連日にわたって繰り広げられた「壮絶」といっていいクインテットによるコラボレーションが創造性においてピークに達したからだ。
演奏体験を重ねることで、リヴァースが自分の役割を体得したといえばいいだろうか。それまでは、本人も「お客さん」的な気分で演奏していたし、メンバーも「ゲスト」的な扱いをしていた。ところが、最終日の演奏は、彼がいて初めて「マイルス・デイヴィス・クインテット」が理想的な形で成立していることを示す内容になった。いまや、リヴァースは完全にグループに溶け込んでいる。その熱いステージがここに甦った。マイルスがこのとき日本で残した記録はすべてが後世に語り継がれるべきものだ。
各地で大反響を呼んだ「第1回世界ジャズ・フェスティヴァル」だが、興行的には大赤字だった。フェスティヴァルがこの1回で終わったのは、それが理由だ。この規模のフェスティヴァルが日本で定着するのは70年代後半である。スポンサーのサポートも必要だし、経済復興はしつつあったにしても、64年の時点では時期尚早だった。
しかし、日本で開催された初の国際的なジャズ・フェスティヴァルは、マイルスの初来日共々、ジャズをさらに深く浸透させた点で、その後の本邦ジャズ・シーンにとって、大きな意義があった
[(c)WINGS 21083046:小川隆夫/TAKAO OGAWA]