
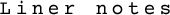
1964年7月の日本公演が終わった直後にサム・リヴァースはマイルス・デイヴィスのクインテットを去り、いよいよウェイン・ショーターが加入してくる。マイルスはジョン・コルトレーンが退団したときにも彼をグループに誘ったが、このときはわずかの差でアート・ブレイキー率いるザ・ジャズ・メッセンジャーズに加入したあとだった。以来、ことあるごとに、マイルスはショーターの加入を熱望していた。そして、彼を迎えるにはいまや最高のメンバーが顔を揃えていた。
「春先から、連日のようにマイルスがわたしの出ているクラブに来たり、家に電話してくるようになった。あるときなんか、どうやって調べたのか、ガール・フレンドと食事をしているレストランにまで電話をしてきた。『ザ・ジャズ・メッセンジャーズのスケジュールが決まっている年末までは移れない』と何度もいったんだ。でも、彼はアート(ブレイキー)に交渉して、7月の仕事が終わったらザ・ジャズ・メッセンジャーズを退団することで話をつけてしまった」(ウェイン)
ブレイキーはこの出来事をどう見ていたのだろう?
「マイルスの気持ちもわかっていたけれど、こちらにだって都合がある。もう少し待ってほしいと何度も頼んだ。でも、マイルスも、ウェインを自分のバンドに迎えたいの一点張りで、こちらが根負けした。ウェインも熱望していたし、このことはほかのメンバーも知っていたから、これ以上引き止めたら、却ってみんなの気持ちを削ぐことになる。そう思い、断腸の思いで退団を認めた。結果として、ウェインにとっても、マイルスにとってもよかったがね」
ウェインには願ってもない移籍だった。以前からマイルスの音楽に興味を持っていた彼は、クインテットに加わって、ザ・ジャズ・メッセンジャーズで演奏していたとき以上の真価を発揮する。
それはマイルスも同じだった。ウェインが加わった最初の作品『マイルス・イン・ベルリン』(コロムビア)を、それ以前に残されたライヴ・アルバムと比較してみれば、このことは明瞭だ。マイルスがこんなに大胆なプレイをしているのもめったにないことである。
事態が進展したのは、日本から戻ったのちの7月中旬から8月初旬にかけてのことだ(8月末の説もある)。ロサンゼルスにいたマイルスのところに、ウェインがザ・ジャズ・メッセンジャーズを辞めるという連絡が入った。そこで、マイルスはエージェントのジャック・ウィットモアに、すぐ彼をグループに迎えるよう指示したのだった。
「ウェインからも電話がかかってきた。だから、『いますぐロスに飛んで来い』といってやった。ずいぶんと待たされたからな。奮発して、ファースト・クラスのチケットを送った。ウェインはそうした待遇に値するミュージシャンだ。才能があるヤツには、それなりの待遇をしなくちゃいけない。そうだろ?」
64年夏、クインテットにウェインが加入した。ここに、ジョン・コルトレーンらを擁していた50年代の黄金クインテットに続く、「第2期黄金クインテット」の幕が切って落とされる。マイルスが38歳、ウェインが30歳、ハービー・ハンコックが24歳、ロン・カーターが27歳、トニー・ウィリアムスが18歳の夏だ。
ただし、これ以前の62年に、ふたりは一度だけレコーディングで顔を合わせたことがある。そのセッションはレギュラー・グループとは別のもので、ウェインのほかに、トロンボーン奏者のフランク・レハク、コンガ奏者のウィリー・ボボ、そしてシンガーのボブ・ドローが加わり、マイルスのクインテットからはポール・チェンバースとジミー・コブが参加した。録音されたのは、〈ブルー・クリスマス〉(コロムビアからリリースされたオムニバス盤の『ジングル・ベル・ジャズ』に収録)、〈ナッシング・ライク・ユー〉(67年に発表されるマイルスのリーダー作『ソーサラー』に収録)、ドローが抜けた〈デヴィル・メイ・ケア〉(シングル盤で最初に発表された)の3曲だ。
初めてマイルスと共演した日のことを、ウェインが回想する。
「レコーディングに参加したいきさつは覚えていない。スタジオで譜面を渡され、リハーサルもなしに録音がスタートした。最初はシンガー(ボブ・ドロー)を入れたセッションで、なかなか調子が合わず、かなりのテイクを重ねた。驚いたのは、マイルスに限れば、ほとんどのテイクがOKだったことだ。イントロだけで失敗したテイクもあったけれど、たいていはマイルス以外のメンバーがミスってストップした」
それが、正式なメンバーとして録音するようになると、そのときとはまったく違うことになっていた。
「レギュラー・メンバーになって気がついたのは、自分さえOKなら、他のメンバーが少しくらいミスっても、マイルスが問題にしないことだった。勢いを大切にしていたし、自分のプレイに全神経を集中させていた。ぼくたちのプレイをチェックするのは、プロデューサーのテオ(マセロ)だ。彼にしても、よほど大きなミスがない限り、もう1テイク録りたいといえる雰囲気じゃなかった」(ウェイン)
ウェインが合流したあと、クインテットは西海岸をしばらくツアーし、それからヨーロッパに飛び立つ。その直前に、グループは人気テレビ番組の『スティーヴ・アレン・ショウ』に出演した。演奏されたのは、〈ノー・ブルース〉〈ソー・ホワット〉〈オール・ブルース〉である。これらはコルトレーン時代と同様、マイルスはマイルス、ウェインはウェインの感じで演奏され、グループ・サウンドと呼べるものは認められない。しかし、マイルスは明らかにウェインのプレイに触発されている様子で、そうした変化が粗い粒子の画面からではっきりと伝わってくる。
テレビ出演を終えた直後のヨーロッパ・ツアーで生まれたのが『マイルス・イン・ベルリン』だ。この作品でも、基本的なスタイルはそれまでと同じ吹き流し的なブローイング・セッションの趣で、これといった新しい音楽性は認められない。
しかしこのときのパフォーマンスが素晴らしいのは、マイルス以下の全員が、それまでになく溌剌としたプレイを繰り広げているからだ。〈マイルストーンズ〉〈枯葉〉〈ソー・ホワット〉〈ウォーキン〉など、お馴染みのレパートリーながら、どのトラックからも従来の殻を破るフレッシュで創造性に溢れたプレイが展開されていく。そのさまを聴くにつけても、「ウェイン効果」が大きく働いていたことは明白だ。
「ここでのウェインはフラッテッド・フィフスをほとんど使っていない。それが新しい響きに繋がった。だから、彼のプレイは、それ以前のコルトレーンやジョージ・コールマンと比べて、明らかに新しいサウンドを有するものになった」
ウィントン・マルサリスがこのアルバムを聴いて、こう教えてくれた。
フラッテッド・フィフスとは、ビバップの時代に入ってから多用されるようになった、センター・キーに対する短5度の音だ。この音をフレーズにちりばめると、ブルージーな響きが強調される。その音を減らしたことで、ブルース色が薄れ、それまでとは異なる響きを獲得した——これがウィントンの指摘だ。
何度も「グラミー賞」に輝き、「ピューリツァー賞」まで受賞して、ジャズ界を代表するトランペッターになったウィントンとぼくは、82年から翌年にかけて、ニューヨークでとなり組だった。当時、注目の新人だったウィントンがマイルスのレコードをひたすら聴きまくっていた姿を何度も目にしている。
ウェインが加わってきたころにマイルスが考えていたのは、過去の伝統や因習の打破だった。レナード・フェザーのインタヴューに対し、彼は、「お定まりのレパートリーはすたれつつあり、これからは多少なりともモダンなものを書く連中の作品を集中的に演奏するようになるだろう」と、予言めいたことを語っている。それは、マイルスがオーネット・コールマンやジョン・コルトレーンなど、フリー・ジャズ派の動きに注目していたこととも無縁でない。
フリー・ジャズとは、音楽の基本であるコード進行や譜割りを無視し、エモーションの赴くまま、文字どおり自由(フリー)に演奏するジャズのことだ。これは、50年代半ばにピアニストのサン・ラやセシル・テイラーが現代音楽から影響を受けた前衛的な手法をジャズに持ち込み始めたことに端を発している。直後には、アルト・サックス奏者のオーネット・コールマンが従来のジャズの枠には収まらない自由な発想で演奏を開始したことでも大きな反響を呼ぶようになった。
その結果、フリー・ジャズは60年代に入ると一大勢力にまで発展していく。このムーヴメントの中心人物のひとりが、マイルスの下から独立したコルトレーンだ。彼は、60年代半ば前後からフリー・ジャズの最先端を行く演奏を始め、後続のミュージシャンに大きな影響を与える存在になっていた。マイルスがフェザーに語ったのも、そんな時期のことだ。
「ウェインが加わって、バンドのサウンドが俄然フリーになった。初日からそうだった。最初に〈ジョシュア〉のワン・フレーズを演奏したとたん、ヤツが絡んできた。その瞬間、リズム・セクションが爆発した。ゾクゾクするほどの興奮だった。リハーサルなんか一度もやっていないのに、ウェインは演奏のツボを心得ていた。ハービーもロンもトニーも、それ以前にレコーディングやセッションで何度もウェインと共演していたから、ヤツの出方がわかっていたんだろう。オレだけが知らなかった。けれど、それがオレに火をつけた。こんなヤツと毎日演奏できるのかと思うと、すっかり有頂天になってしまった」(マイルス)
ウェインも初めてマイルスのクインテットで演奏した日のことを覚えていた。
「緊張していて、どんな演奏をしたかは忘れた。『いつも通りにやればいい』とハービーにいわれてた。こちらにしたって、それしかやりようがないから腹をくくった。終わったあとに、楽屋でマイルスが『このヤロー』という感じで殴りかかるふりをした。そういうときの彼が最高に満足していることは、しばらくしてわかった」
そういう状況下で残されたのが、ウェインを加えたクインテットによるこのライヴだ。グループが約3週間のヨーロッパ・ツアーに出たのは64年9月下旬である。このときの模様は、初日を飾った9月25日のベルリン・コンサートが発表されたことで大きな話題を呼ぶようになった。ツアーは同作を残した9月25日に始まり、以下のスケジュールで10月11日まで続く。17日間で10か所のコンサートはいつものヨーロッパ・ツアーに比べると少し短い。
September 25, Berlin Philharmonie
September 26, Concertgebouw, Amsterdam
September 29, Le Theatre Municipal, Lausanne
September 30, Kongresshaus, Zurich
October 1, Salle Pleyel, Paris(2 concerts)
October 3, Johanneshov Isstadion, Stockholm
October 4, KB-Hallen, Copenhagen
October 6, Messuhalli, Helsinki
October 8, Stadthalle, Sindelfingen(2 concerts)
October 11, Teatro dell’ Arte, Milan
ほかに、フランクフルトとバロセロナでもコンサートはスケジュールされていたが、これらはキャンセルされた模様だ。残された各地のパフォーマンスを聴くと、最初に登場した『マイルス・イン・ベルリン』の出来がいちばんいい。それは、まだほとんど共演経験のなかったウェインの緊張感が、本人のプレイにもグループのパフォーマンスにも好ましい形で作用したからだ。
それに比べると、最終日となったこのミラノ・コンサートでは、初日のような研ぎ澄まされた緊張感はやや薄められている。それでも、演奏は文句なしの出来映えだ。比較の問題であって、『マイルス・イン・ベルリン』を聴かなければ、この作品を最上位の1枚として評価することにやぶさかでない。
マイルスはいつもと同じで、自分のスタイルを最高の状態で表出させる。興味深いのはウェインとリズム・セクションの絶妙なやりとりだ。ウェインのプレイはとても新参者によるものとは思えない。すでに、さまざまなところでリズム・セクションの3人とは共演していた。その経験がものをいったのだろう。マイルスとの相性も、歴代のテナー・サックス奏者——ジョン・コルトレーン、ハンク・モブレー、ジョージ・コールマン——と比べて遜色がない。
「こんなヤツと毎日演奏できるのかと思うと、すっかり有頂天になってしまった」——この言葉は誇張でない。そのことを伝えているのがこのライヴ・パフォーマンスだ。
[(c)WINGS 21083047:小川隆夫/TAKAO OGAWA]