
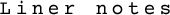
マイルス・デイヴィスがハード・バップに見切りをつけてモード・ジャズに目を向けた背景には、1956年に起こったジョン・コルトレーンの一時的な退団が少なからず影響している。マイルスとギル・エヴァンスが新しいオーケストラ作品のアイディアについて話し合っていた同年10月のことだ。
そのときの事情は、J.C. トーマスが書いた『コルトレーンの生涯』(『スイングジャーナル』社)の中で、こう描写されている。
「ある日、セロニアス・モンクがカフェ・ボヘミアの楽屋に立ち寄ったところ、マイルスがトレーンの顔を平手打ちし、さらに、腹に一発パンチを食らわせたのを目撃した。ふたりは、トレーンの演奏のことで喧嘩をしていたのだろう。コルトレーンは無抵抗のまま、マイルスのなすがままになっていた。だが、モンクは違った。彼は、トレーンにいったのだ。『サキソフォンを吹きたいからって、こんなことまで我慢する必要はない。わたしのところで仕事をしてみないか』。こうして、セロニアス・モンク・カルテットが生まれたのである。ベースのウィルバー・ウェアとドラムスのシャドー・ウィルソンを加えて」
ボクシング・ジムで本格的なトレーニングをしていたマイルスのパンチはさぞかし強烈だったことだろう。しかし、体格で勝るコルトレーンが無抵抗だったのは賢明だ。ふたりが本気で喧嘩をしたら、ジャズの大きな財産が傷ついていたかもしれない。
ギルとのオーケストラにマイルスの関心が向けられた理由のひとつに、コルトレーンの退団があったことは間違いない。オーケストラへの意欲が高まったことと、コルトレーンが退団した事実が相乗効果となって、マイルスは以前ほどレギュラー・メンバーに固執しなくなった。その後の彼が、しばらくの間、断続的な形でしかレギュラー・コンボで活動していないことからも、これは推察ができる。
このころのマイルスは、どちらかといえば、コンボについては「どうでもいい」の気持ちになっていた。そして、コルトレーンに代わってはソニー・ロリンズが迎えられ、すでに決まっていたいくつかのギグが消化される。
「このときは短期間ということで、空いている時間だけマイルスの誘いに応じた。音楽的なことはいっさいいわれなかった。好きに吹かせてくれた。ただ、マイルスとわたしとでは、1年前に比べてスタイルにだいぶ違いが出てきていた。マイルスはクールで、わたしはホットにブローするのが好きだった。彼は、そのコントラストを狙っていたのかもしれない。でも、わたしはこのコンビが一時的なものだと思っていたし、実際にそうだった」(ロリンズ)
ロリンズを迎えたクインテットで「カフェ・ボヘミア」の仕事を終えたマイルスは、直後の11月に、以前からスケジュールされていたヨーロッパ・ツアーに出発する。これはマイルスのほか、レスター・ヤングとモダン・ジャズ・カルテットに、フランスやドイツのミュージシャンを組み合わせた一種のパッケージ・ショウだった。一座は、アムステルダム、チューリッヒ、フライブルク、パリなどでコンサートを開いている。
ヨーロッパ・ツアーを終えて、マイルスは12月にニューヨークに戻ってくる。その後はコルトレーンを復帰させてツアーに出たものの、この間にも、コルトレーンは以前から依存するようになっていた麻薬やアルコールで問題を起こしてしまう。彼の悪癖に拍車をかけていたのが、同じく麻薬常習者でもうひとりのバンド・メンバー、フィリー・ジョー・ジョーンズだ。そのこともマイルスにはわかっていた。そこで、しばらくツアーしたのちの4月(57年)に、今度はふたりをクビにしたのだった。
マイルスの下を去ったコルトレーンはどうしていたのか? 今回も、ただちにモンクのカルテットに参加している。そして、マイルスがニュー・クインテットで「カフェ・ボヘミア」に出演していたころ、モンクのカルテットは同じくニューヨークにあった人気クラブの「ファイヴ・スポット」に長期出演をして、のちに「伝説的ライヴ」と呼ばれる名演を繰り広げていた。
しかし、マイルスはやはりオリジナル・クインテットが忘れられなかった。あれだけの演奏が残せたグループだから当然だ。11月には、コルトレーンとフィリー・ジョーを呼び戻し、レッド・ガーランドとポール・チェンバースとでクインテットを復活させている。ただし、このあたりのマイルスの心情はよくわからない。コルトレーンに対し、愛憎相半ばする気持ちを持っていたのだろう。
マイルスは、演奏面で絶大な信頼をコルトレーンに寄せていた。それでも私生活の面では、どうしても我慢ができなかった。ただし、コルトレーンはこのころまでに麻薬とはすっかり縁を切っていた。その結果の復帰だったのかもしれない。それからやはり、ロリンズとのコンビでは、音楽的に無理があったとも考えられる。
その後のマイルス・クインテットではメンバーの出入りが続く。アルト・サックスのキャノンボール・アダレイが参加して6重奏団に拡大されたのが58年1月のことだ。5月にはピアニストがガーランドからビル・エヴァンス、ドラマーがフィリー・ジョーからジミー・コブに代わっている。10月末をもってエヴァンスが退団し、一時的にガーランドが復帰するも、年明けからウィントン・ケリーがレギュラー・ピアニストの座につく。
59年3月と4月は、このメンバーとエヴァンスで(1曲だけケリーが参加)傑作『カインド・オブ・ブルー』(コロムビア)が吹き込まれる。その後(9月)にキャノンボールがグループを抜け、59年秋以降は、マイルス、コルトレーン、ケリー、チェンバース、コブの布陣で活動が継続されていく。
そして迎えた60年。マイルスはこの年の春と秋に2回のヨーロッパ・ツアーを行なっている。前者はコルトレーンを擁したクインテットのラスト・ツアーで、後者はソニー・スティットが参加してのものだ。どちらもノーマン・グランツ・プロデュースのJ.A.T.P.(Jazz At The Philharmonic)ツアーに組み込まれたステージである。3月21日から4月10日まで行なわれたツアーの名称は「ノーマン・グランツ・J.A.T.P.・プレゼンツ・ジャズ・ウィナーズ 1960」。
このときの模様は何種類かの海賊盤で聴くことができる。公式盤としてコロムビアが2018年に発売した『マイルス・デイヴィス&ジョン・コルトレーン/ザ・ファイナル・ツアー [ブートレグ・シリーズ Vol.6]』は、初日(3月21日)にパリの「オランピア劇場」で行なわれた2回のセット、翌晩のストックホルムの2回のセット、24日にコペンハーゲンの「チヴォリ・コンサート・ホール」で残された1回のセットをコンプリート化したものだ。
22日のストックホルム・コンサートは、これ以前にも『マイルス・デイヴィス&ジョン・コルトレーン/ライヴ・イン・ストックホルム 1960』(ドラゴン)としてLPが出ているし、10月のヨーロッパ・ツアーと併せた『マイルス・デイヴィス・ウィズ・ジョン・コルトレーン&ソニー・スティット・イン・ストックホルム 1960 コンプリート』(DIW)という4枚組CDもリリースされている。ただし、春のツアーを聴くなら[ブートレグ・シリーズ]が量的にいちばん充実している。
これは、マイルスが自身のグループを引き連れて行なう初のヨーロッパ・ツアーでもあった。前年に録音した『カインド・オブ・ブルー』が渡欧に合わせて発売され、キャノンボール・アダレイとビル・エヴァンスは抜けていたものの、ほぼ同じメンバーのコンサートが各地で大きな話題を呼ぶ。
コルトレーンはしばらく前から独立したいと強く願っていた。マイルスはあの手この手で引き留めていたが、「いやだ」という人間を縛りつけておくわけにはいかない。そこで、「ツアーが終わったら退団していい」という条件で参加させたのである。そんなコルトレーンが心情を吐露するかのように、ライヴでは激しい演奏を連続させる。
「荷物はサキソフォンとエアライン・バッグに洗面用具だけ。トレーンはその仕事をしたくなかったが、マイルスに説き伏せられた。移動のバスではいつもわたしのとなりにすわっていたが、落ち着かない様子だった。暇さえあれば窓の外を眺めたり、東洋風の音階をソプラノ・サックスで吹いたりしていた」(ジミー・コブ)
コンサートでは、コルトレーンの過激な演奏が賛否両論を生む。そこで急遽実施されたのが、ストックホルムのコンサート終了後にスウェーデン人DJのカール=エリック・リングレンが行なったインタヴューだ。これも『マイルス・デイヴィス&ジョン・コルトレーン/ザ・ファイナル・ツアー [ブートレグ・シリーズ Vol.6]』に収録され、日本盤のブックレットには翻訳がつけられている。
そこでの会話が興味使い。
「あなたは怒っているのですか?」
「いや、そうじゃない。怒っているように聴こえるかもしれないが、一度にさまざまなことを試しているから、たくさんの音が出るんだ」
アメリカに戻って、残されていた2、3の出演契約を終えると、コルトレーンは晴れてマイルスのグループから独立し、しばらくあとに自身のカルテットを結成する。
*
マイルスが初めて自分のグループで行なったこのときのヨーロッパ・ツアーは各地で大反響を巻き起こす。公演先は、フランス、スウェーデン、デンマーク、西ドイツ、スイス、オーストリア、オランダなどで、本作には4月9日のオランダ公演が収められている。軽やかにトランペットを吹くマイルスと、重厚な響きを湛えたコルトレーン。ふたりの対照的なプレイが演奏を盛り上げる。
とはいえ、ふたりのコンビネーションはほとんど認められない。退団が決まったコルトレーンもマイルスに負けず劣らずの優れたソロを披露する。手を抜いたり、投げやりだったりする態度はいっさいなし。そこに、音楽に対する誠実さが示されている。
モード曲の〈ソー・ホワット〉が面白い。マイルスのプレイにモーダルな響きが感じられないからだ。メロディックではないものの、コード進行をなぞったフレーズの連続が軽やかな印象を与える。それに比べると、コルトレーンのプレイは重量感がいっぱいだ。とくに、「シーツ・オブ・サウンド」と形容される独特のフレージングを中心にした後半が素晴らしい。
お馴染みになった〈ラウンド・ミッドナイト〉では、テーマ・パートでマイルスがメロディを崩して自在な表現に徹する。「みんなメロディは知っているから、いまさらきちんと演奏するまでもない」といったところか。きっかけ程度にメロディが出て、あとはミュートでのアドリブになってしまう。コルトレーンにソロがバトン・タッチされる際に用いられる例のフレーズが聴かせどころだ。これで、彼も気持ちよくソロに入っていける。
そのコルトレーンはツアーを終えた直後に独立する。マイルスの落ち込みはかなりのものだった。最後のフィラデルフィアではほとんど泣き崩れそうになって、退団をアナウンスしたという。よほど手放したくなかったのだろう。
[(c)WINGS 21103049:小川隆夫/TAKAO OGAWA]