
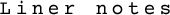
「ドラムソロが好きだったことは一度もないね」
この発言通りに、チャーリーはベースやギター、そしてボーカルという他の楽器とともに演奏し、そこでのビート感、スウィング感を大切にしたドラマーだ。
チャーリー・ワッツ ― 1941年6月2日生まれ・ふたご座。2021年8月24日死去(享年80歳)。
12歳でジャズに興味を持ち、17歳でジャズの生演奏を聴くためにクラブに通いだす。学生時代にはジャズクラブでドラムの演奏を始め、やがてアレクシス・コーナーと出会う。1962年には彼のバンド、ブルース・インコーポレイテッドに加入しブルースやR&Bをプレイ。そこに「エルモ・ルイス」と名乗るブロンドのギタリスト、ブライアン・ジョーンズも加わってくる。
1962年4月7日、イーリング・ジャズ・クラブを訪れたミック・ジャガーとキース・リチャーズがブライアン、チャーリーらのライヴを目撃。ミック、キースとブライアンが意気投合して共同生活を始めるが、チャーリーはアレクシスのバンドでの演奏を継続。そこにビル・ワイマンが参加してくる。
当時、アレクシスのバンドには後にクリームを結成するジンジャー・ベーカー(drum)やジャック・ブルース(bass)など錚々たるメンバーがたちかわり在籍。ロンドンでのミュージシャン養成スクールの役割を担う。
1962年4月21日、チャーリーはイーリング・ジャズ・クラブでチャック・ベリーの「アラウンド・アンド・アラウンド」を、ミックとキースを交え初めて一緒に演奏。このときのベースはディック・テイラー。
翌1963年1月12日にチャーリーはビルとともに、ミックたちのグループで初めてライヴ演奏をする。プロにはなりたくないと考えていたチャーリーは、この頃アレクシスのバンドを辞めていたのだが、なぜかストーンズに惹かれて加入を決める。
「やつらは狂ってたよ。だってギャラもなく、嬉しそうにただギグをやってたんだから。奴らと関わると収入はぐっと落ちるのは目に見えていた。でも僕もちょうどR&Bに興味を引かれ始めてたし、なぜかやつらが気に入ったんだ。それで、いいよ、参加するよって言っちゃったんだ」
これで遂にローリング・ストーンズのメンバーが揃うこととなる。バンドはすぐにIBCスタジオでデモ録音を敢行。アンドリュー・オールダムがマネージャーに就き、デッカ・レコードと契約を結ぶ。6月には「カム・オン」でデビューを果たした。
「たまたま世界一のロックンロール・バンドにジャズドラマーが入ってるだけさ」
自身は常にジャズドラマーのスタンスを崩さなかったチャーリー。彼のエイトビートは一種独特のビート感があり、キースのタメの効いたギターカッティングと共にストーンズの独特のグルーヴを生み出している。よりディープなストーンズ・ファンによると、そのキースとチャーリーのリズムのわずかな間に、ひとつひとつ音符を置いていくようなビルのベースワークが、ストーンズ最大の魅力ともいう。
チャーリーのドラミングで有名なのが、スネアを叩くときにハイハットを刻むの止める「ハット抜き」である。これはスネアの音を強調し、よりバックビートがヘヴィになる。1972年のステージではすでに、そのスタイルを始めていて、ストーンズのグルーヴが確立された時期と合致している。
またディスコビートの基本スタイルである、「1小節に4発バスドラム頭打ち」を、「ミス・ユー」のみならずロックンロールでも取り入れるなど、グルーヴへの探究心は人一倍なのだろう。
「スウィングするロックドラマーはヤツだけさ。ヤツのドラムじゃなきゃロックはロールしない」とはキースの弁。確かにチャーリーのドラムは、きらびやかなフィルインや、派手なタム回しなどはなく、一聴すると下手なドラマーなのかと思う人も少なくないだろう。筆者も高校生の頃、バンドを組もうとしてチャーリー役のドラマーを探すのだが、皆一様に、あんな地味なドラムは叩きたくないと言われるのがオチだった。グルーヴを理解するにはまだ若すぎたのか、ハードロックやパンクなど燃える音楽へ流れていくが、チャーリーのドラムにこそ、ジャズ、ブルース、ロックンロールを繋ぐグルーヴの秘密があるのだ。ひとたびそれを知れば、ロックが、ロールが、そしてロック&ロールが楽しくて仕方なくなるだろう。
本作ではストーンズ加入前の1962年から、1967年の『サタニック・マジェスティーズ』までの音源から、チャーリーのドラムプレイが際立つトラックを選りすぐって収録した。そして重要なのは、現行の公式CDでは聴けないレアなミックスばかりで構成されていることだ。ローリング・ストーンズの核心を担う、チャーリーのビートを体感して頂きたい。
■01:Get Off Of My Cloud
Los Angeles, RCA Studios, Hollywood / 5th September 1965
初期ストーンズでチャーリーといえばこれをハズすことはできない。2小節まるまるドラムだけのイントロ。スネアの強烈なフィルインにミックの「イエェ」が重なり「ひとりぼっちの世界(邦題)」の幕開けだ。右チャンで大きく聴こえるハンドクラップはステレオ・ミックスの証し。ブライアンの弾く単音のギターリフが通常より大きく聴こえる貴重なミックスだ。
■02:19th Nervous Breakdown
Los Angeles, RCA Studios, Hollywood / 8th – 10th December 1965
次は1966年2月にリリースされた「19回目の神経衰弱(邦題)」だ。ツインギターの鮮やかなイントロから始まるが、エンディングのビルのベースのグリッサンドも話題になった。チャーリーのライドシンバルの刻みが、ボ・ディドリーの曲で使われるマラカスの様に揺れていて、実はそれこそがこの曲のキモだと思う。
公式では一度も発表されたことのないリアル・ステレオ・ミックスでの収録。キースのギターリフにブライアンの低音リフが重なって始まるイントロが、2分27秒過ぎのブレイク部分では、逆にブライアンからキースのリフへと展開するのもシャレている。ここはステレオ・ミックスでこそ効果的なのだ。なぜ公式で発表されないのか、まったくもって謎である。
■03:(I’m Your)Hoochie Coochie Man (Alexis Corner’s BLUES INCORPORATED)
BBC “Jazz Club”, London, Paris Theatre / 12th July 1962
さぁ、これはチャーリーがストーンズに加入する前、アレクシス・コーナーのバンドで残したBBCセッションでの音源だ。ベースはなんとジャック・ブルース。本作はこの3曲目から、ほぼ時系列に沿った収録なので、チャーリーのドラミングの変遷が聴き取れるはずだ。
ボーカルはシリル・ディビスで、彼はアレクシスと同じく英国でのR&Bシーンを広めることに尽力しながら、1964年に胸膜炎で早すぎる死を迎える。
personnel : Charlie Watts (dr)/Alexis Korner (gtr)/Cyril Davies (vo, harm)/Dave Stevens(p)/Jack Bruce (string bass)/Dick Heckstall-Smith (sax)
■04:Baby What’s Wrong
■05:Diddley Daddy
■06:I Want To Be Loved
“IBC Denos” London, IBC Studios, Portland Place / 11th March 1963
ちょうど今、ビートルズの「レット・イット・ビー」のミックスで時の人となっているエンジニア/プロデューサーのグリン・ジョンズが、まだIBCスタジオの新人だった頃に、このストーンズの初のレコーディングを手がけている。デビュー前のデモとしてファンには有名な音源だが、ここには3曲を収録。チャーリーにとっても、アレクシスとのBBCセッションでの一発録り以来の本格的なレコーディングだ。
シンプルなドラムが初々しい「Baby What’s Wrong」、一転して2小節ごとにフィルインを叩く「I Want To Be Loved」など、曲に求められるまま実直なドラミングが潔い。このテープでレコード会社との契約を取り付けようという思惑だったのだろうが、買い手はつかず、結局マネージャーになるアンドリュー・オールダムがテープを買い取る。戦略家のオールダムの初仕事は、このデモ音源でも素晴らしいピアノを聴かせてくれるイアン・スチュワートをメンバーから外してローディとすることと、キース・リチャーズの名前から‘s’を取り、キース・リチャードとすることだった。
■07:Come On
BBC “Saturday Club”, London / 23rd September 1963
オールダムの辣腕で、5月にはデッカ・レコードと契約を結んだストーンズは「カム・オン」でデビューを果たす。これはその約3ヶ月半後のBBCでのライヴ・バージョン。ミックのボーカル、ブライアンのハープとコーラス、キースのギター、ビルのベースとコーラス。そしてチャーリーのドラム。最もプリミティブなストーンズのサウンドが聴ける。
同日にツアーで英国にきていたボ・ディドリーもBBCで収録を行っており、チャーリーとビルがリズム隊を務めたが、音源は発掘されていない。
■08:Go Home, Girl
London, De Lane Lea Studios, Holborn / 14th November 1963
セカンド・シングルは、ビートルズのジョンとポールの力を借りて「彼氏になりたい(邦題)」を11月にリリース。直後にEP用に「マネー」と「ポイズン・アイヴィー」をレコーディングするが、そのときにこの曲も録音された。ビートルズがカバーした「アンナ」や「ユー・ベター・ムーブ・オン」などの作者であるアーサー・アレキサンダーの曲。公式としては、いまだ完全未発表である。
■09:Everybody Needs Somebody To Love
Los Angeles, RCA Studios, Hollywood / 2nd November 1964
米国では「テル・ミー」や「タイム・イズ・オン・マイ・サイド」がヒットし、セカンドアルバムは米国での方が早くリリースされるなど、米国人気が盛り上がりを見せるなか、英国でのセカンドアルバム「No.2」の1曲目に収録されたロング・バージョン。ここには貴重なステレオ・ミックスで収録。
■10:The Last Time
Los Angeles, RCA Studios, Hollywood / 17th and 18th January 1965
ストーンズとして遂にオリジナル・ソングで英国1位を獲得した曲。ここには貴重なステレオ・ミックスで収録。公式のモノミックスと比べてボーカルが鮮明だ。
■11:(I Can’t Get No) Satisfaction
Los Angeles, RCA Studios, Hollywood / 11th – 12th May 1965
ストーンズの代名詞でもある「サティスファクション」。チャーリーはスネア、バスドラ、ハイハットを首尾一貫延々と刻み続け、フィルインの一切ないドラムと、ジャック・ニッチェによるタンバリンのリズムパターンが見事。クラブミュージックと同じ完全ループビートだが、なぜもこんなに人間くさいのか。右チャンネルにアコギが振られた、このステレオ・ミックスは現行CDでは聴くことができない。
■12:Built For Comfort (Alexis Corner’s BLUES INCORPORATED)
BBC “Band Beat”, London / July 1962
本CDの3曲目と同じくアレクシス・コーナーのバンドでのBBCセッション音源だが、ロング・ジョン・ボルドリーがボーカルを取っている。ドラムはチャーリーとの記録があるが、確認は取れていない。皆さんは聴いてみて、どう思われるだろうか。まだストーンズ加入前のチャーリーを音だけで確証を得るのはなかなか難しいところだ。このときのセッションでは「(Night Time Is) The Right Time」も、チャーリーがドラムとして販売されたこともあるが、リサーチしたところジンジャー・ベイカーの可能性が高く、本CDには収録されていない。
personnel : Charlie Watts (dr)/Alexis Korner (gtr)/Long John Baldry (vo)/Ronnie Jones (vo)/Jack Bruce (bass)/Keith Scott (p)/Dick Heckstall-Smith (sax)/Cyril Davies (harm)
■13:Mother’s Little Helper
Los Angeles, RCA Studios, Hollywood / 8th – 10th December 1965
カウントの声から収録されたバッキング・トラック。「疲れを癒すためお母さんは錠剤を飲む」・・ドラッグソングのさきがけだ。ビルのベースをツービートで支えるチャーリー。ボーカルがないため、演奏が聴き取りやすい。チャーリーの細かなハイハットさばきなどを聴いて欲しい。
■14:Under My Thumb
Los Angeles, RCA Studios, Hollywood / 7th – 11th March 1966
ボーカルが小さく(途中からは消える箇所も)録音されたワーキング・ミックス。キースのエレキ&アコギ、ブライアンのマリンバ、ドラムとベース。それぞれの楽器の構造を聴き取ることができるだろう。
■15:Paint It, Black
Los Angeles, RCA Studios, Hollywood / 7th – 11th March 1966
これもボーカルが小さく録音されたワーキング・ミックス。「赤いドアを黒く塗ってしまいたい。他の色なんていらない。すべて黒になればいい」・・曲タイトルにカンマがあるかなしかで意味も変わる(レコード会社が勝手につけてしまったようだ)。カンマが入ると「黒く塗れよ、黒人」となってしまうため人種差別ではと取り沙汰されたことも。実際の歌詞は、ボブ・ディランの「はげしい雨が降る」の一節、「ここの世界では黒しかなく」からの影響と、読書家のミックがJ・ジョイスの小説「ユリシーズ」から着想を得たようだ。中近東風のフレーズ、シタールの響き。チャーリーの強烈なツービートが曲を支えている。
■16:Have You Seen Your Mother, Baby, Standing In The Shadow?
London, IBC Studios / 31st August – 2nd September 1966
このサイケデリックな曲も、いまだに公式ではステレオ・ミックスは発表されたことがない。ここにはステレオ・ミックスで収録。ジャック・ニッチェのアレンジによるブラスセクションがラウドだが、混沌としたサウンドの最終ミックスにキースは納得できていなかったという 。珍しくチャーリーはフロアタムを強烈に叩きまくる。狂ったようなピアノの連打はJ・ニッチェとキース。とっ散らかってはいるが、この時代でしかなし得なかったサウンドといえるだろう。「お前のお母さんが暗闇に立っているのを見たことはあるかい?」という歌詞で、メンバー全員が女装してのジャケットは、1966年という時代では強烈だったはず。
■17:We Love You
London, Olympic Sound Studios / 17th – 21st May 1967
ミック、キース、ブライアンと薬物所持での逮捕事件が続く中、制作された。ニッキー・ホプキンスによるピアノの連打と、ブライアンのメロトロンが不気味に迫るも、「この世界に愛を」なる邦題も付けられた。ここにはボーカルなしのセッション・テイクを収録。
■18:She’s A Rainbow
London, Olympic Sound Studios / 17th – 21st May 1967
「We Love You 」とほぼ同じ楽器編成ながら、一転してカラフルなナンバー。これもセッション・テイクから収録。
2021年7月22日、コロナ渦で延期されていたストーンズのツアーが9月26日のセントルイス公演から再開されると公式アナウンス。
2021年8月5日、医師の判断により病気療養のため、チャーリーがツアーに参加しないことが発表される。代役はチャーリーの指名によりスティーヴ・ジョーダン。
2021年8月24日、チャーリー・ワッツの死去の報。
「次に死ぬロック・ミュージシャン」リストの筆頭だったキースをはじめ、ストーンズのメンバーは、それぞれが闘病をのり越えてきていた。チャーリーは2004年に喉頭がんを。ミックは2019年に心臓弁置換手術。ロン・ウッドは2017年に肺がん、2020年に小細胞がん。同じようにチャーリーも必ず復帰するものと信じていたため、突然の訃報は驚きだった。同時に襲う喪失感。以前からメンバー自身が繰り返し発言していた「チャーリーがいなきゃストーンズじゃないさ」。これを受けるなら、かつてのレッド・ツェッペリンのように解散という選択肢が脳裏をよぎった。
しかしストーンズはツアーを再開することを選んだ。「続けることをチャーリーが願っている」と。
リズムの要を失った世界最高のロックンロール・バンドは、2021年10月現在、米国ツアーを敢行中である。来年、ストーンズは結成60周年を迎える。
CROSS(the LEATHERS/島キクジロウ&NO NUKES RIGHTS)